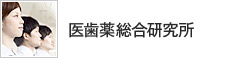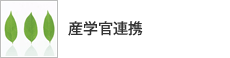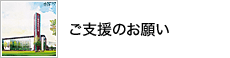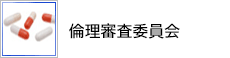睡眠医療学科
学科紹介
大学附属の睡眠医療センター(内丸)で、睡眠生理や睡眠障害診断評価の技術である精密な睡眠検査を実施し「睡眠に関わる健康障害」を広範囲に取り扱う学科です。基礎となるのは、精神神経学や神経内科学に関連する睡眠障害や呼吸調節機能障害とそれらを対象とする呼吸管理、さらには高血圧や肥満、脂質異常、糖尿病などの合併症を対象とする内科的診療について学びます。さらに、肥満外科や顎顔面外科、矯正歯科との連携による睡眠時無呼吸症の治療管理もテーマとしています。
- 社会医学系専攻(睡眠の障害に基づく疾病や障害の探求)
社会医学としての睡眠医学に関する広い知識を有し、睡眠関連疾患(過眠症・不眠症)と社会不適合、危険作業従事者における日中過眠をはじめとする社会医学的課題への対処や早期診断と治療法の開発など、社会医学的診療・研究が行える人材を育成する。
主な研究内容
- 高度肥満に対する、減量・代謝改善手術が合併する閉塞性睡眠時無呼吸症候群に治療法として有用かの前向き研究を行っている。
- 病態解明や診断方法の確立を目的として、睡眠や食行動などに関係する神経ペプチドの測定による研究を行っている。
- 睡眠の障害やその原因となる内科的病態や解剖学的異常などを解析する(歯科分野との連携)。
学生へのメッセージ
○睡眠は単に眠るにあらず
睡眠の異常が日常の判断や記憶、運動機能などの高次脳機能に悪影響を与えることは、誰しもが経験しています。近年、睡眠の障害が脳機能のみでなく、循環器疾患や代謝性疾患にも重大な影響を与えていることが次々に明らかにされています。睡眠医療学は内科・外科系のみでなく、歯科や検査医学との境界領域に位置し、呼吸、循環、代謝、中枢神経機能などを扱う医療従事者にとって、最も新しい研究分野のひとつといえます。
研究の相談・指導役となる先輩たちは本コース設置以前から睡眠関連の研究で学位を取得し、同時に臨床医として内科や呼吸器科、睡眠医療専門医の試験にも合格しています。さらに広く国内外への留学ルートもあり、出身者5名は既に県内で自ら内科や睡眠のクリニックを主宰しています。